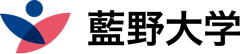看護学研究科
看護学専攻の教育目標
- 高い倫理観と豊かな人間性をもって、サービスを受ける者の視点に立った実践ができる。
- 最新の知見・技術の獲得を怠らず、専門性を高めることに努め、科学的根拠に基づいた実践ができる。
- 看護専門職者として専門的役割を示すロールモデルとなって、指導力を発揮して教育的役割を果たすことができる。
- 保健・医療・福祉の様々な領域で看護組織及び看護ケアをマネジメントし、関連他職種と連携し組織化することができる。
- 看護の科学的根拠を探求し、新たなケア技術やシステムの開発を試みることができる。
教育課程の構成
構成
実践看護分野
- 成育看護学
- 成人・高齢者看護学
- 精神看護学
- 災害看護学
- 助産学
看護マネジメント分野
- 地域保健看護学
- 看護管理学
- 感染管理学
取得可能な学位
学位

- 修士(看護学)
取得可能な免許
- 養護教論専修免許状※
- 助産師(国家試験受験資格)※
※指定科目の単位を取得した者
学びの流れ
共通科目
- 看護理論
- 発達医療保健論
- 国際看護論
- 看護倫理
- 臨床心理学
- 地域高齢者生活支援論
- 看護教育論
- 医療保健システム論
- 教育学特論
- 看護研究方法論
- 医療統計学
専門科目
実践看護分野
- 成育看護学特論
- 成人・高齢者看護学特論
- 災害看護学特論
- 成育看護学演習
- 成人・高齢者看護学演習
- 災害看護学演習
- 助産学特論
- 精神看護学演習
- 特別研究
- 助産学演習
- 精神看護学特論
看護マネジメント分野
- 地域保健看護学特論
- 看護管理学特論
- 感染管理学特論
- 地域保健看護学演習
- 看護管理学演習
- 感染管理学演習
- 特別研究
助産学分野
- 基礎助産学Ⅰ(助産学概論)
- 地域母子保健
- 助産学実習Ⅰ(周産期・ハイリスク)
- 基礎助産学Ⅱ(基礎助産学)
- 助産診断・技術学演習Ⅰ(妊娠期)
- 助産学実習Ⅱ(保健指導・助産所)
- 基礎助産学Ⅲ(胎児・新生児学)
- 助産診断・技術学演習Ⅱ(分娩期)
- 助産学実習Ⅲ(産後ケア・女性生殖器)
- 基礎助産学Ⅳ(健康教育)
- 助産診断・技術学演習Ⅲ(産褥・新生児期)
- 特別研究
- 助産管理
- 助産診断・技術学演習Ⅳ(ハイリスク)
養成する人材像
本研究科で養成する人材像は、大きく次の4つです。
- 高い倫理観に基づいた深い学職と識見及び豊かな人間性をもち、サービスを受ける者の視点に立った実践ができる人材。
- 学際的な視点とリサーチマインドをもって、実践の場での課題を発見し、保健医療福祉に関して深めた知識から、課題解決のための新たなケア技術やシステムの開発を試みることができる研究者。
- 看護専門職者として専門的役割を示すロールモデルとなって、指導力を発揮して教育的役割を果たすことができる人材。
- 保健・医療・福祉のさまざまな領域で看護組織及び看護ケアをマネジメントし、関連他職種と連携し協働することができる人材。
看護学研究科(修士課程)
看護学専攻学位審査基準
1.修士論文審査・判定基準
修士論文の審査は以下の基準で審査され、審査委員の採点に基づいて合否の判定がなされる。
- 研究目的が明確であること。
- 研究の意義が明確であること。
- 十分な文献検討が行われていること。
- 研究方法が適切であること。
- 必要な倫理的配慮がなされていること。
- 研究結果が正確かつ明確に述べられていること。
- 研究結果に対する考察が適切であること。
- 修士論文作成要領に即していること。
2.最終試験評価・判定基準
最終試験(口頭試問)は以下の基準(ディプロマ・ポリシー)で評価され、審査委員の採点に基づいて合否の判定がなされる。
- 高い倫理観に基づいた深い学識と識見及び豊かな人間性をもち、サービスを受ける者の視点に立った実践ができる。
- 学際的な視点とリサーチマインドをもって、実践の場での課題を発見し、保健医療福祉に関して深めた知識から、課題解決のための新たなケア技術やシステムの開発を試みることができる。
- 看護専門職者として専門的役割を示すロールモデルとなって、指導力を発揮して教育的役割を果たすことができる。
- 保健・医療・福祉の様々な領域で看護組織及び看護ケアをマネジメントし、関連多職種と連携し協働することができる。
3.審査体制・方法
- 審査体制
修士論文審査及び最終試験は、研究科委員会において学位審査委員会を設けて行う。- 学位審査委員会は、研究科委員会において選出された本学又は他の大学院、研究所等の研究指導・研究指導補助を担当できる6名以上の学位審査委員をもって組織する。
- 学位審査委員より主査1名、副査2名を選出する。
- 前項の定める主査は、教授でなければならない。ただし、学位を取得しようとする者の指導教授は主査になることはできない。
- 審査方法
- 学位審査委員により修士論文審査を行う。
- 修士論文発表会を開催し、学位申請者による口頭発表、また主査1名、副査2名を中心に発表内容について最終試験(口頭試問)を行い、学位審査委員により評価を行う。
- 研究科委員会を開催し、(ⅰ)(ⅱ)の結果をもとに合議の上、最終的な合否判定を行う。
研究科長メッセージ
ともに学び看護の未来を
切り拓いていきましょう。


- プロフィール
- 齋藤 祥乃Yoshino Saito
-
京都府出身
関西医科大学附属第一看護専門学校卒
京都大学医療技術短期大学部助産学特別専攻修了
滋賀医科大学大学院医学系研究科修士課程(看護学)
滋賀医科大学大学院医学系研究科博士課程(医学)
関西医科大学附属男山病院助産師、京都保健衛生専門学校専任教員を経て、2014年4月より藍野大学医療保健学部看護学科講師、2020年教授、2025年より看護学研究科長に就任。
日本母性衛生学会、日本助産師会、看護理工学会に所属。
藍野大学は、大阪府で初の私立看護師養成大学として設立され、学校法人として55年以上にわたり看護師教育の伝統を築いてきました。本学の看護学研究科は、高度な専門性を備えた医療職の養成に対する関連病院や施設からの強い期待を受け、変化の激しい社会の要請に応えながら、研究的思考能力を持つ専門性の高い看護職の育成を目指して2015年に設置されました。そして本年、設立から11年目を迎えます。
現在、医療機関では在院日数の短縮が進み、さまざまな専門職が連携・協働して問題解決に取り組むチーム医療が求められています。その中で、看護職が専門性を高め、自律的に活動することは、安全で質の高い医療の提供につながるため、看護職への期待はますます高まっています。また、医療の急性期化が進む一方で、在宅医療や地域保健、疾病予防といった地域に根ざした医療の重要性も増しており、生活支援や看取りまでを視野に入れた高度実践看護職の育成が求められています。さらに、近年では大規模な自然災害の発生が相次いでおり、専門的な知識や技術の習得に加え、適切な判断力をもって医療連携をコーディネートできる高度な実践能力、さらには現場の課題を探求し、問題解決のための研究を推進できる能力を持つ人材の育成が求められています。
大学院教育は、看護の継続教育の一環として、基礎教育や臨床現場で培った知識と経験を土台に、さらに専門的な知識と実践能力を高め、研究を通じて新たな知見を創出することを目的としています。本学の看護学研究科では、「実践看護分野」と「看護マネジメント分野」の2つの専門分野を設け、それぞれの分野で高度な教育を実践しています。ゼミ、実習、論文作成を通して、ともに学び、看護の未来を切り拓いていきましょう。