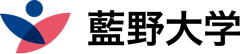更新日
(⻄暦.年.⽉.⽇) |
2025.08.01 |
| 氏名(漢字) |
杉山 芳生 |
| 氏名(フリガナ) |
スギヤマ ヨシキ |
| 氏名(ローマ字) |
SUGIYAMA Yoshiki |
| 所属部署(学部・学科) |
医療保健学部 理学療法学科 |
| 職名 |
講師 |
| e-mail |
y-sugiyama{@}pt-u.aino.ac.jp({@}は@に置き換えてください)
|
| 略歴 |
| 年.月 |
大学・学部・学科、大学院・専攻名、機関名・
所属部署・職名等 |
| 2016.3 |
三重大学教育学部学校教育教員養成課程 卒業 |
| 2019.3 |
京都大学大学院教育学研究科博士前期課程 修了 |
| 2020.4 |
日本学術振興会特別研究員(DC2)(2022年3月まで) |
| 2022.3 |
京都大学大学院教育学研究科博士後期課程 修了 |
| 2022.4 |
藍野大学医療保健学部理学療法学科(現在に至る) |
|
| 取得学位 |
博士(教育学)【京都大学】 |
| 資格・免許 |
| 年.月 |
概要 |
| 2016.3 | 小学校教諭一種免許状 |
| 2016.3 | 中学校教諭二種免許状(技術) |
| 2016.3 | 中学校教諭一種免許状(保健体育) |
| 2016.3 | 高等学校教諭一種免許状(保健体育) |
|
| 研究分野 |
大学教育学、教育方法 |
| 所属学会 |
大学教育学会、日本教育工学会 |
| 主な研究テーマ |
PBL、初年次教育 |
| 主要研究業績 |
| 種別 |
題目 |
単著・
共著の別 |
掲載誌・機関誌名・ページ等 |
発行
年月 |
| 学術論文(査読有) |
ジグソー法の要素を加えた医療系多職種連携PBLの実践 |
共著 |
日本教育工学会論文誌, 49(1): 145-152. |
2025.3
|
| 著書 |
第22章 経験学習―キャンパスとしての都市と人的ネットワーク― |
共著 |
『ミネルバ大学の設計書』(松下佳代監訳)東信堂, pp.351-362. |
2024.5
|
| 口頭発表 |
初年次学生が有する論証の型に関する試行調査 |
単著 |
大学教育学会第45回大会 |
2023.6
|
| 学術論文(査読有) |
PBLの実行可能性―藍野大学におけるシンメディカル科目の実施から― |
単著 |
京都大学大学院教育学研究科紀要,68: 343-356. |
2022.3
|
| 学術論文(査読有) |
2つのPBLの歴史的展開と学習プロセスのモデル |
単著 |
京都大学高等教育研究, (27): 68-79. |
2021.12
|
| 学術論文(査読有) |
PBL継続事例における持続要因の検討―新潟大学歯学部の事例をもとに― |
共著 |
大学教育学会誌, 42(2): 49-58. |
2020.12
|
| 学術論文(査読有) |
PBLの持続可能性の条件―医療分野における中断・縮小事例の分析に基づいて― |
共著 |
京都大学高等教育研究, (25): 59-62. |
2019.12
|
| 学術論文(査読有) |
パフォーマンス評価における学生の自己評価・相互評価は妥当な評価に近づきうるか―市民オンライン推論能力を素材として― |
共著 |
京都大学高等教育研究, (25): 13-24. |
2019.12
|
| 学術論文(査読有) |
PBL (Problem-Based Learning) の多分野展開における変容―三重大学を事例として― |
共著 |
大学教育学会誌, 40(1): 73-82. |
2018.5
|
| 口頭発表 |
アクティブラーニングの評価の論点と課題 |
共著 |
大学教育学会第39回大会 |
2017.6
|
|
| 特許等の知的財産 |
|
| 主な学会活動等 |
|
| 現在の担当科目 |
|
教育内容・方法の
工夫や教科書・教材・
講義資料の作成と活用
などについて |
学生が主体となって課題に取り組む活動を中心に授業を構成している。また、LMSを活用することで、授業の復習や課題の管理、学生同士の交流、教員への質問等の促進を図っている。 |
今後提供できる科目や
教育内容 |
|
教育に関する著作・
講演・発表など |
| 種別 |
題目 |
単著・
共著の別 |
掲載誌・機関誌名・ページ等 |
発行
年月 |
|
| 主な社会活動等 |
|
| 受賞・学術賞など |
|
| 上記以外の特記事項 |
|
個人ホームページ
アドレス |
|